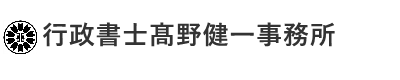こんな方には特に遺言書の作成をおススメします
遺言書は「資産家や高齢者が作るもの」と思われがちですが、実はさまざまな方にとって重要なものです。遺言書を残しておくことで、自分の意思を確実に伝え、家族や親族のトラブルを防ぐことができます。
1. 子どもがいない夫婦
子どもがいない夫婦の場合、遺言書がないと、配偶者が全財産を相続できるとは限りません。たとえば、夫が亡くなった場合、妻が財産のすべてを受け取るわけではなく、夫の両親や兄弟姉妹にも相続権が発生します。
特に、夫婦どちらかの両親が存命であれば、相続財産の一部が親に渡ることになります。これを防ぎ、配偶者にすべての財産を遺すためには、遺言書を作成しておくことが重要です。
2. 内縁関係のパートナーがいる方
法律上の婚姻関係にないパートナー(内縁の妻や夫)には、法定相続権がありません。そのため、何の手続きをしなければ、パートナーが遺産を受け取ることはできません。
「長年一緒に暮らしていたのに、財産を一切受け取れない」という状況を避けるためには、遺言書を作成し、内縁のパートナーに財産を遺す意思を明確にしておく必要があります。
3. 事実婚や同性パートナーがいる方
事実婚や同性婚のパートナーも、現行の日本の法律では法定相続人にはなりません。つまり、遺言書がないと、パートナーは何も相続できないのです。
大切なパートナーに財産を残したい場合は、遺言書を作成し、財産を譲る意思をしっかりと示しておきましょう。
4. 相続人同士のトラブルを防ぎたい方
相続が発生すると、相続人同士で「誰が何をどれだけ受け取るのか」という問題が発生します。場合によっては、家族が争う原因にもなります。
特に、
兄弟姉妹の仲が悪い
親族に借金を抱えている人がいる
先妻や後妻の間に子どもがいる
こういったケースでは、遺産分割をめぐって紛争が起こりやすくなります。遺言書があれば、事前に財産の分配を指定できるため、相続トラブルを回避できます。
5. 会社を経営している方
会社経営者にとって、遺言書の作成は非常に重要です。経営者が急逝した場合、相続手続きが滞ることで、会社の経営が一時的に混乱し、最悪の場合、倒産につながることもあります。
特に、後継者を決めている場合は、遺言書で明確に指名しておくことが重要です。これにより、会社の円滑な事業承継が可能になります。
6. 財産を特定の人や団体に遺したい方
遺言書がない場合、遺産は法定相続人に自動的に分配されます。しかし、「特定の人や団体に財産を残したい」と考えている場合、遺言書が必要です。
例えば、
面倒を見てくれた友人に財産を譲りたい
お世話になった介護施設に寄付したい
慈善団体やNPOに財産を寄付したい
こうした希望を叶えるためには、遺言書に明確に記載することが必要です。
7. 障がいのある家族がいる方
障がいを持つ子どもや家族がいる場合、適切な遺産の分配を行わないと、生活に困る可能性があります。
例えば、
知的障がいのある子どもがいる場合、遺産をどのように管理するかを明記しておく
生活保護を受けている家族がいる場合、遺産が原因で受給資格を失わないように配慮する
こういった事情を考慮し、遺言書を作成することで、大切な家族の生活を守ることができます。
8. 特定の財産を特定の人に譲りたい方
「この家は長男に継がせたい」「この土地は次男に相続させたい」など、特定の財産を特定の人に譲りたい場合、遺言書がないと意図した通りに相続されない可能性があります。
例えば、不動産が関係する場合、法定相続のままでは共有名義となり、後々のトラブルの原因になりかねません。遺言書を作成することで、希望通りの財産分配が可能になります。
9. 自分の葬儀や供養について希望がある方
遺言書には、財産の分配だけでなく、葬儀や供養の希望を記載することもできます。
例えば、
「家族だけで静かに葬儀をしてほしい」
「散骨してほしい」
「菩提寺で供養してほしい」
こうした希望を遺言書に残しておけば、遺族が迷わずに対応できます。
まとめ
遺言書は「資産家のためのもの」と考えられがちですが、実は多くの人にとって重要なものです。
子どもがいない夫婦
内縁関係・事実婚・同性パートナーがいる方
相続トラブルを避けたい方
会社経営者
特定の人や団体に財産を遺したい方
障がいのある家族がいる方
財産を特定の人に譲りたい方
葬儀や供養の希望がある方
このような方々は、ぜひ遺言書の作成を検討してください。遺言書を作成することで、自分の意思を確実に残し、大切な人々の未来を守ることができます。
遺言書の作成には、専門家(弁護士や司法書士、行政書士)に相談するのもおすすめです。適切な形で遺言を残し、安心した未来を準備しましょう。